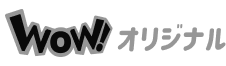なぜ日本のライブコマースは『流行らない』と言われたのか?メルカリ・BASE撤退から学ぶべき5つの教訓と復活の鍵
2025-08-15 19:07:03
目次

序論:日本ライブコマース市場のパラドックス – 「失敗」ではなく「市場最適化」の物語
「ライブコマース 日本 流行らない」「ライブコマース 失敗」といったキーワードで検索するユーザーの懐疑的な視線は、決して的外れではありません。2019年から2020年にかけて、フリマアプリ最大手のメルカリが「メルカリチャンネル」を終了させ、ネットショップ作成サービスのBASEが「BASEライブ」から撤退するなど、大手プラットフォームの相次ぐ撤退は、日本のライブコマース市場に「失敗」という強い烙印を押しました。この時期の出来事は、多くの事業者やマーケターに、日本市場におけるライブコマースの将来性への疑念を抱かせたのです。
しかし、この「失敗」の物語は、物語の序章に過ぎませんでした。本稿が解き明かすのは、2019年から2020年の出来事が、市場の終焉ではなく、むしろ健全な**「市場最適化(マーケット・コレクション)」のプロセス**であったという事実です。中国で爆発的な成功を収めたモデルをそのまま持ち込んだ初期の試みは、日本の独特な消費者文化や市場構造と相容れず、その不適合が大手サービスの撤退という形で現れたのです。
ここに、ひとつの大きなパラドックスが存在します。もし日本のライブコマースが本当に「失敗」したのだとすれば、なぜ今、驚異的な成長が予測されているのでしょうか。市場調査によれば、日本のライブコマース市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)33.8%という驚異的なペースで成長し、2030年までに73億1510万米ドル(約1兆円超)に達すると予測されています。この数字は、過去の「失敗」という通説とは全く相容れない未来を描き出しています。
本レポートは、このパラドックスを解き明かすための専門的な分析を提供します。まず、メルカリやBASEの撤退劇を深く掘り下げ、その背景にある戦略的な判断を解剖します。次に、初期の市場が苦戦した5つの根本的な原因を、中国市場との比較を通じて多角的に分析します。そして最後に、その「失敗」の灰の中から立ち上がった、ユニクロに代表される「日本独自の成功モデル」を徹底解剖し、今日の市場で成功を収めるための具体的な5つの教訓を提示します。これは、過去の失敗を乗り越え、力強い復活を遂げつつある日本のライブコマース市場の真実を解き明かす、戦略的評価レポートです。
TikTokトップ級セラーの販売テクニックがここに!「7LIVE」で最先端のライブコマースを体感してみてください。
▶[7LIVEをチェック]
第1章 2019-2020年の撤退の波:「失敗」という物語の解体
ライブコマースが「流行らない」という認識を決定づけたのは、2019年から2020年にかけての主要プラットフォームの相次ぐサービス終了でした。しかし、これらの出来事を単なる「失敗」として片付けることは、市場の本質を見誤らせます。ここでは、メルカリとBASEの事例を中心に、撤退の背景にあった戦略的な文脈を客観的に分析します。
1.1 メルカリチャンネル(2019年7月終了):事業崩壊ではなく、戦略的ピボット
メルカリが2019年7月に「メルカリチャンネル」を終了した際、その公式な理由は「グループ全体での経営資源の再配置」でした。これは単なる言い訳ではなく、当時のメルカリの経営状況を反映した、極めて合理的な経営判断だったのです。
この決定が下された2019年6月期第3四半期、メルカリは米国事業への先行投資や、モバイル決済サービス「メルペイ」の立ち上げに伴う巨額の投資により、連結で59億8100万円もの営業赤字を計上していました。国内のフリマ事業は堅調であったものの、会社全体としては、将来の成長エンジンと位置づける事業へリソースを集中投下する局面にありました。
メルカリチャンネル自体は、コメントが目で追えないほどの勢いで流れたり、スタンプで画面が埋め尽くされたりするなど、一部で熱狂的な盛り上がりを見せる瞬間もありました。しかし、メルペイや米国事業といった、より大きなスケールでのリターンが期待される戦略的プロジェクトと比較した際、その投資対効果(ROI)は十分なものではなかったと推察されます。
つまり、メルカリチャンネルの終了は、「ライブコマースという事業モデルがメルカリ内で失敗した」というよりも、「企業全体のポートフォリオ戦略の中で、優先順位が見直された」と解釈するのがより正確です。限られた経営資源を、最も成長ポテンシャルの高い事業に集中させるという、大企業の成長過程における典型的な戦略的ピボット(方向転換)の一例であり、これをライブコマース市場全体の失敗と結論づけるのは早計でしょう。
1.2 広がる同調:BASE、楽天、Yahoo!の追随(2020年)
メルカリの撤退に続き、2020年には「BASEライブ」(2020年3月終了)、「Rakuten Live」、「Yahoo!ショッピングLIVE」といった主要プラットフォームも次々とサービスを終了、もしくは縮小しました。この一連の動きは、市場全体が停滞しているかのような印象を強く与えました。
しかし、ここで注目すべきは、これらの撤退が起こった「時期」です。2020年初頭は、新型コロナウイルスのパンデミックにより、日本全体のEコマース市場が未曾有の活況を呈し始めた時期と完全に一致します。経済産業省の調査によれば、2020年の物販系BtoC-EC市場規模は、前年比21.7%増という驚異的な伸びを記録しました。
この事実は、極めて重要な示唆を与えてくれます。もし、当時のライブコマースプラットフォームが日本の消費者や事業者にとって本当に価値のあるものだったならば、EC需要が爆発的に高まったこの追い風を受けて、むしろ急成長を遂げていたはずです。しかし、現実はその逆でした。
この逆説的な状況が証明しているのは、問題が「オンラインで物を買う」という行為そのものではなく、当時提供されていた**「ライブコマースの“モデル”」**にあったということです。消費者のEC利用意欲が最高潮に達している状況下でさえ、これらのプラットフォームが支持を得られず撤退に至ったという事実は、そのフォーマット、コスト構造、あるいはユーザー体験が、日本の市場環境と根本的にミスマッチしていたことを何よりも雄弁に物語っています。このミスマッチこそが、次章で詳述する「流行らなかった」本当の理由です。
第2章 ミスマッチの解剖学:初期市場が苦戦した5つの根本原因
なぜ、EC市場全体が活況を呈する中で、初期のライブコマースは失速したのでしょうか。その答えは、中国の成功モデルを深く理解することなく、表層的に模倣してしまったことにあります。ここでは、日本の市場が直面した5つの根本的なミスマッチを、中国市場との比較を通じて解き明かします。
2.1 原因1:「KOL」と「インフルエンサー」の断絶 – プロの販売員という役割の欠如
初期の日本市場における最大の誤算は、「KOL(Key Opinion Leader)」と「インフルエンサー」を同義語として扱ってしまった点にあります。
中国のライブコマースを牽引するKOLは、単なる有名人ではありません。彼らは、成果報酬(コミッション)を主な収益源とし、商品を売ることに特化した**「プロの販売員」**です。彼らは膨大な商品知識を蓄え、視聴者からのリアルタイムの質問に即座に答える柔軟性を持ち、表情や声量に至るまで、販売スキルを徹底的に磨き上げています。
一方、2017年頃の日本で起用されたのは、既存の「インフルエンサー」や芸能人でした。彼らはフォロワーとの関係構築やブランドのPRには長けていたものの、リアルタイムで商品を売り切るための専門的な販売スキルやマインドセットを持っていなかったのです。その役割は「プロモーター」であり、「クローザー」ではありませんでした。
この機能的な違いは、致命的なパフォーマンスの差を生みました。ブランドアンバサダーに、トップセールスマンの仕事を依頼するようなもので、求められるスキルセットが根本的に異なっていたのです。結果として、視聴者数は集まっても購入には繋がらず、企業は期待したほどの成果を得ることができませんでした。
2.2 原因2:文化と消費者行動のミスマッチ – 「信頼」と「衝動」の文脈差
ライブコマースが中国で成功した背景には、特有の社会課題と消費者文化がありました。しかし、その前提は日本では通用しなかったのです。
- 信頼性の前提条件の違い: 中国のEC市場では、かつて偽物や粗悪品が横行した歴史があり、消費者は「信頼できる人(KOL)が実際に使って見せてくれる」ことに大きな価値を見出しました。一方、日本ではAmazonや楽天といったプラットフォームへの信頼が既に確立されており、実店舗・ECともに品質の高い商品が手に入るため、ライブコマースに「真贋の確認」という役割を求める動機が弱かったのです。
- 購買スタイルの違い: 日本の消費者は、商品の品質や情報を慎重に吟味し、比較検討した上で購入する傾向が強いことで知られています。初期のライブコマースが煽った「今すぐ買わないと損!」というような、衝動買いを促すハイテンションなスタイルは、この冷静な購買文化とは相性が悪かったと言えます。
- 消費を楽しむ文化の違い: 中国には「独身の日(ダブルイレブン)」のように、国全体が熱狂する巨大なセールイベントがあり、これがライブコマースの爆発的な需要を支えています。日本には、これに匹敵するような大規模な消費イベント文化が存在せず、ライブコマースを日常的に利用する強い動機付けに欠けていました。
要するに、中国のライブコマースは「信頼の欠如を補完し、衝動買いを加速させる」という、市場に存在する課題を解決し、既存の文化を増幅させるソリューションでした。対照的に、日本では「特に解決すべき課題のない市場に、新たな行動を強制する」ソリューションとして持ち込まれたため、消費者の心に響かなかったのです。
2.3 原因3:未成熟なプラットフォームエコシステム – 「機能」と「生態系」の差
成功するライブコマース体験は、視聴から購入、決済、配送までがシームレスに連携した、摩擦のない導線設計を必要とします。
中国の「淘宝直播(タオバオライブ)」のようなプラットフォームは、巨大ECモール「淘宝網(タオバオ)」の中に深く統合された「生態系(エコシステム)」として設計されています。ユーザーはライブを見ながら、数タップで購入から決済(Alipay)までを完了できます。これは、ライブ動画が買い物体験の核心に組み込まれていることを意味します。
一方、日本の初期プラットフォームの多くは、既存のアプリに後付けされた「機能(フィーチャー)」に過ぎませんでした。メルカリチャンネルはフリマアプリの一機能であり、視聴から購入までの体験が完全にシームレスだったとは言い難いでしょう。さらに、一部のライブ配信プラットフォームでは、規約で外部ECサイトへの直接誘導が禁止されているケースもあり、コマース(商取引)への導線が寸断されていました。
この技術的・戦略的な断絶は、ユーザー体験を損ない、コンバージョン率を低下させる大きな要因となりました。中国が「エコシステム」を構築したのに対し、日本は単なる「機能」を点在させたに過ぎず、その差が競争力の差となって現れたのです。
2.4 原因4:「コピー&ペースト」戦略の罠 – ローカライゼーションの欠如
初期の参入企業の多くは、「中国で流行っているのだから、日本でも成功するはずだ」という安易な発想に囚われていました。これは、市場のローカライゼーションの重要性を軽視した、典型的な戦略的傲慢であったと言えるでしょう。
彼らが模倣したのは、ライブコマースの「仕組み(ライブ動画+ショッピングカート)」であり、その背景にある「力学(なぜそれが中国で機能するのかという文化的・経済的理由)」ではありませんでした。販売手法、コンテンツの内容、そして根本的な価値提案を、日本の消費者心理に合わせて最適化(アダプテーション)するのではなく、単に複製(レプリケーション)しようとしたのです。
その結果、生まれたのは、日本の視聴者には共感されない、魂の抜けた模倣品でした。文化的にそぐわない演出や、消費者のニーズを捉えきれていない商品選定は、当然ながら低いエンゲージメントと売上しか生み出せず、プラットフォームの撤退へと繋がっていきました。
2.5 原因5:ROIの謎と企業の躊躇 – 事業としての魅力の欠如
最終的に、初期のライブコマースモデルは、最も基本的なビジネスのテストをクリアできませんでした。それは、出店する事業者に対して、明確で説得力のある**「投資対効果(ROI)」**を提示できなかったことです。
企業にとって、ライブ配信の制作、サーバーコスト、インフルエンサーへの報酬などは決して小さくない投資でした。しかし、前述の4つの理由により、売上は期待外れに終わることが多かったのです。これでは、事業として継続することは難しいでしょう。
さらに、多くの企業は、既存の販売チャネルであるAmazonや楽天で十分に満足しており、コストがかかる上に成果が不透明なライブコマースに多額の投資を行う強い動機を見出せませんでした。明確なビジネスケースがなければ、企業は動きません。事業者の支持を得られなかったプラットフォームが、存続の危機に瀕したのは必然でした。
第3章 フェニックスの瞬間:再発明と「日本独自モデル」の台頭
2019年から2020年にかけての撤退の波は、日本のライブコマース市場の終わりではありませんでした。それは、市場が自らの過ちから学び、日本独自の成功法則を発見するための「産みの苦しみ」だったのです。現在、市場は「失敗」の物語を覆し、力強い成長を遂げています。その復活の鍵は、中国モデルの模倣を捨て、「専門性」と「信頼関係」を核に据えた、全く新しいアプローチにありました。
3.1 中核的なイノベーション:「雇われインフルエンサー」から「社内の専門家」へ
市場復活の最大の原動力となった戦略転換は、配信者を外部のインフルエンサーに委託するのをやめ、製品を最も深く理解している自社の社員を主役に据えたことです。店舗の販売員、ブランドマネージャー、美容部員、さらには商品の生産者といった「内部の専門家」が配信を行うことで、ライブ配信は単なる宣伝から、信頼性の高い「コンサルテーション」へと昇華しました。このアプローチは、外部のインフルエンサーでは決して提供できないレベルの「本物感(オーセンティシティ)」と深い商品知識をもたらし、視聴者との間に強固な信頼関係を築く基盤となったのです。
3.2 ケーススタディ:ユニクロ「LIVE STATION」– オウンドメディア戦略の金字塔
この新しい潮流を最も象徴するのが、ユニクロが展開する「UNIQLO LIVE STATION」です。ユニクロの戦略が画期的なのは、ライブコマースを短期的な販売チャネルとしてではなく、自社のアプリやウェブサイト内で展開する**「オウンドメディア」**として位置づけている点にあります。その最大の目的は、目先の売上ではなく、既存のファンや顧客との関係性を深化させることなのです。
- スタッフが主役: 配信の主役は、商品への情熱と深い知識を持つ店舗スタッフです。彼らの言葉には、企業のマーケティングメッセージにはない、現場ならではのリアリティと説得力が宿ります。
- リアルな課題解決: コンテンツは徹底してユーザー中心に設計されています。「様々な身長のスタッフが着比べ、フィット感を伝える」「骨格診断別に似合うワンピースを提案する」「梅雨を快適に過ごすためのアイテムを紹介する」など、顧客が日常的に抱える具体的な悩みや疑問に寄り添います。これは、視聴者が本当に知りたい情報を提供するという、顧客本位の姿勢の表れです。
- コミュニティの醸成: リアルタイムのコメント機能を通じて、双方向のコミュニケーションを重視し、視聴者が「自分の声が届いている」と感じられる空間を創出しています。これにより、単なる売買関係を超えた、ブランドを中心とした忠実なコミュニティが形成されるのです。
この戦略は絶大な成功を収め、年間累計視聴者数は1,000万人を突破しました。ユニクロの成功が示すのは、日本市場で最も効果的なモデルが、商品を「売る(Selling)」ことではなく、顧客に「尽くす(Serving)」ことであるという真理です。彼らはライブコマースという手法を用いて、質の高いコンサルテーション、すなわち「デジタルおもてなし」を提供しています。その結果として生まれる信頼が、自然な形で購買へと繋がり、長期的なブランドロイヤルティを育んでいるのです。
3.3 専門分野での成功:信頼性は専門性に宿る
日本型モデルのもう一つの特徴は、画一的なアプローチではなく、業界や商品の特性に応じて最適化されている点にあります。
- 化粧品業界 – デジタル上のビューティーカウンター: 資生堂やクリニークといったブランドは、プロのビューティーコンサルタントやメイクアップアーティストを起用し、百貨店の化粧品カウンターで提供されるような、専門的でパーソナルな接客体験をオンラインで再現しています。視聴者は、自身の肌質やメイクの悩みについて、専門家から直接、的確なアドバイスを受けることができます。これは、初期の市場が抱えていた「プロの配信者不足」という課題に対する、完璧な回答です。
- 食品・地方産品 – 生産者の物語: この分野での成功は、消費者を「作り手」や「産地」と直接結びつけることからもたらされます。京都の農家が自身の畑から京野菜の魅力を語り、創業110年の豆菓子屋がその歴史と情熱を伝え、長野の牧場からチーズ職人が日々のこだわりを配信する。このような生産者の顔が見えるストーリーは、何よりの品質保証となり、消費者に安心感と共感を与えます。商品そのものだけでなく、その背景にある物語が、強力な付加価値となるのです。
これらの成功事例に共通するのは、その商品カテゴリーにおいて消費者が最も信頼する「専門家」を配信者に立てている点です。化粧品なら美容のプロ、食品なら生産者。それぞれの文脈で最も説得力のある人物が、ライブというフォーマットを通じてその専門性を発揮するのです。これは、極めて戦略的で的を絞ったアプローチであり、初期の「コピー&ペースト」モデルとは対極にあります。
3.4 表:日本におけるライブコマースモデルの進化
この戦略的な転換を簡潔に可視化するため、初期モデルと進化した日本モデルを比較します。この「ビフォーアフター」のフレームワークは、市場がどのように学習し、適応していったかを明確に示しています。
| 特徴 | 初期モデル (2017-2020年) | 進化した日本モデル (2021年-現在) |
|---|---|---|
| 主な配信者 | 汎用的なインフルエンサー、芸能人 | 社内の専門家(店舗スタッフ、美容部員)、生産者 |
| 中核的な目的 | 短期的な衝動買いの誘発 | 長期的な関係構築、ファンコミュニティ形成、ブランド信頼の醸成 |
| プラットフォーム戦略 | 第三者プラットフォーム(メルカリ、BASE) | オウンドメディア(ユニクロアプリ等)、統合ECサイト、SNSは集客ツール |
| 価値提案 | 「今だけ安い!」(価格主導) | 「あなたに合うものを見つけます」(サービス・専門性主導) |
| 重要業績評価指標 (KPI) | 即時売上、視聴者数 | エンゲージメント率、顧客ロイヤルティ、顧客生涯価値 (LTV) |
| 文化的類似性 | 活気ある露天市場 | 心遣いの行き届いた百貨店カウンター、生産者の顔が見える直売所 |
第4章 今日の市場で成功するための5つの実践的教訓
これまでの分析から、現代の日本市場でライブコマースを成功させるための、具体的で実践可能な5つの戦略的教訓を導き出すことができます。これらは、過去の失敗を避け、日本独自のモデルの長所を最大限に活用するための行動指針です。
教訓1:インフルエンサーを雇うな、ブランドアンバサダーを育てよ
成功の鍵は、外部のインフルエンサーに高額な報酬を支払うことではなく、自社の内に眠る最も価値ある資産、すなわち「社員」に投資することにあります。店舗スタッフ、商品開発者、カスタマーサポート担当者など、日々製品に触れ、顧客と対話している彼らこそが、最も信頼性の高いブランドの代弁者です。彼らの製品への情熱と深い知識は、どんなに有名なインフルエンサーの推薦よりも、視聴者の心を動かす力を持っています。彼らを育成し、配信の主役として輝かせるための社内体制を構築することが、持続可能な成功への第一歩となるでしょう。
教訓2:販売チャネルではなく、コミュニティを構築せよ
ライブ配信を単発の販売イベントと捉えてはなりません。ユニクロの「LIVE STATION」が示したように、その真の価値は、ブランドとファンが集い、交流する「コミュニティの場」を創出することにあります。視聴者からのすべての質問に丁寧に答え、コメントに真摯に反応し、彼らが「大切にされている」と感じられる体験を提供することが重要です。信頼に基づいたコミュニティが育てば、売上は一過性のプロモーションの結果としてではなく、コミュニティの活動の自然な帰結として生まれてくるでしょう。
教訓3:「デジタルおもてなし」を極めよ
日本の消費者が最も価値を置くものの一つが、きめ細やかな「おもてなし」の心です。この文化をデジタル空間で体現するのが「デジタルおもてなし」に他なりません。強引な売り込みではなく、顧客の潜在的なニーズを先読みし、丁寧で思慮深いアドバイスを提供するのです。例えば、アパレルであれば体型カバーの方法を、化粧品であれば肌質に合わせた使い方を、食品であれば最適な調理法を提案する。この質の高いコンサルテーションを通じて、顧客の課題を解決するというサービス精神こそが、厳しい目を持つ日本の消費者の信頼を勝ち取るための鍵となります。
教訓4:舞台を賢く選べ – オウンドメディア vs. ソーシャルプラットフォーム
配信場所を安易にInstagramやYouTubeに限定してはなりません。ユニクロのように、自社のウェブサイトやアプリといった「オウンドメディア」で配信することは、極めて強力な戦略となり得ます。オウンドメディアでの配信は、最もロイヤルティの高い優良顧客と直接エンゲージメントを深める機会を提供し、ブランドの世界観を完全にコントロールすることを可能にします。一方、InstagramやLINEといったソーシャルプラットフォームは、オウンドメディア上の本配信へと視聴者を誘導するための「集客ツール」として活用するのが賢明な使い分けです。
教訓5:売上を超えた「配信の目的(Why)」を定義せよ
成功するライブ配信には、単に「商品を売る」という目的を超えた、明確な「存在理由(Why)」があります。自社の配信は、何のために存在するのか? 顧客を教育するためか? ブランドの裏側にある物語を伝えるためか? 生産プロセスの透明性を高めるためか? それとも、地方創生に貢献するためか? このように、より高次の目的を明確にすることで、コンテンツは深みを増し、視聴者の共感を呼び、単なる販売活動を超えた価値を生み出すことができるのです。
結論:未来はライブであり、そしてそれは日本独自のものである
2019年から2020年にかけての「失敗」の物語は、日本のライブコマース市場にとって、不可欠で生産的な市場最適化のプロセスでした。業界は、自らの市場に適合しない海外モデルを脱ぎ捨て、試行錯誤の末に、日本の文化と消費者価値観に深く根差した成功方程式を発見したのです。それは、「専門性」「サービス」「本物感」を三本柱とする、新しい形のコミュニケーションです。
過去の「流行らない」というレッテルを乗り越え、市場は今、力強い成長軌道に乗っています。2030年までに市場規模が73億米ドルに達するという予測は、もはやこれがニッチなトレンドではなく、Eコマースにおける主要なチャネルへと進化しつつあることを示しています。さらに、ライブコマースを含む日本のライブストリーミング市場全体は、2030年には167億米ドル規模に達すると見込まれており、そのポテンシャルは計り知れません。
もはや問われるべきは、ライブコマースが日本で成功するか「どうか」ではありません。企業が、この日本独自に進化した形態を、いかに戦略的に活用できるか「どうか」です。時代遅れの「失敗」の物語から脱却し、「デジタルおもてなし」を核とした、文化的感受性の高いアプローチを受け入れること。この進化の本質を理解した企業にとって、その先に広がる機会は、極めて大きいと言えるでしょう。
TikTokトップ級セラーの販売テクニックがここに!「7LIVE」で最先端のライブコマースを体感してみてください。
▶[7LIVEをチェック]
参考資料
- コンテンツピラーとコンテンツ案
- 「メルカリチャンネル」約2年でサービス終了 | 事業撤退, accessed August 8, 2025.
- 「BASEライブ」提供終了のお知らせ|ネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」 - note, accessed August 8, 2025.
- Japan Live Commerce Market Size & Outlook, 2024-2030, accessed August 8, 2025.
- 「メルカリチャンネル」7月8日に終了へ 理由は「経営資源の再配置」 ライブコマースに見切り, accessed August 8, 2025.
- 日本のライブコマース市場は今後どうなる?中国と比較した日本の課題や成功させるためのポイントを徹底解説 - LIVURU, accessed August 8, 2025.
- メルカリ、BASE、楽天。なぜ有力企業のライブコマースサービスは終了したのか? - note, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースが日本で流行らないって本当?日本ならではの成功事例を紹介 【snsforce】, accessed August 8, 2025.
- jetb.co.jp, accessed August 8, 2025.
- 【2021年7月発表】2020年EC市場規模・EC化率の分析と解説。メーカー企業が今後とるべき戦略, accessed August 8, 2025.
- 日本国内のEC市場規模, accessed August 8, 2025.
- 令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査), accessed August 8, 2025.
- ECの物販系分野の市場規模が21.71%増!2020年統計に見るECの成長と今後の可能性, accessed August 8, 2025.
- 中国のライブコマース事情から読み解く!日本で成功する方法 【snsforce】, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースにおけるKOLとは?KOCやインフルエンサーとの違いについて解説 - HandsUP, accessed August 8, 2025.
- 【中国】KOL・KOCとは?ランク別活用術と注意点 | COLUMN - VECTOR, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースが日本で流行らないと言われている理由は?日本の現状と成功事例を解説, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースが日本で流行らない3つの理由!ECで活用する方法と成功事例を紹介 - FORCE-R, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースの歴史を知ろう!日本と中国の違いと将来とは? - ライバーハウス, accessed August 8, 2025.
- What is live commerce? Benefits and examples in Japan - Stripe, accessed August 8, 2025.
- 日本でライブコマースが普及しない5つの背景を解説 - EBISUMART, accessed August 8, 2025.
- 10年で約100兆円の市場規模に!急成長を遂げた中国ライブコマース市場の「これまで」と「これから」【前編】 | テテマーチ株式会社, accessed August 8, 2025.
- 越境ライブコマース完全ガイド|中国攻略法 - 株式会社エフカフェ, accessed August 8, 2025.
- 【2025年最新版】ライブコマースとは?メリット・デメリットや相性がいい商材、成功事例などを徹底解説 - W2, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースの市場規模は?日本で流行らないと言われている理由を解説 - studio15, accessed August 8, 2025.
- 2025年注目のライブコマースとは?日本で変化するライブ配信の成功事例と売れる業界や商品を解説! - 動画制作・映像制作会社ならムビサク, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースの課題は成功へのカギ!失敗談を知って自社の戦略に反映させよう 【snsforce】, accessed August 8, 2025.
- アパレル業界のライブコマース事例5選!成功に導くたった5つの..., accessed August 8, 2025.
- 【ライブコマースの成功事例まとめ】自社で再現する方法を解説 【snsforce】, accessed August 8, 2025.
- 【事例分析】UNIQLOが「インフルエンサーなし」のライブ配信で..., accessed August 8, 2025.
- 年間の視聴者数1000万人突破! ユニクロのライブコマースが好調な..., accessed August 8, 2025.
- ライブコマースの成功事例10選!日本での成功の秘訣は? - ライズアース, accessed August 8, 2025.
- 化粧品業界のライブコマース事例6選 - ウェビナビ, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースの最新動向と成功事例|売上アップの秘訣とは? - RUBY GROUPe, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースと食品業界は相性がいい?メリットや事例、成功の..., accessed August 8, 2025.
- 創業110年の豆菓子をライブコマースで販売!テレビショッピングで学んだ“売れる配信術”【食品・楽豆屋】 - futureshop, accessed August 8, 2025.
- ライブコマースで新たな消費者接点づくり ライブコマースサービス「Live kit」が変える 企業のマーケティング - BIPROGY, accessed August 8, 2025.
- Japan Live Streaming Market Size & Outlook, 2023-2030, accessed August 8, 2025.